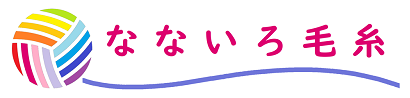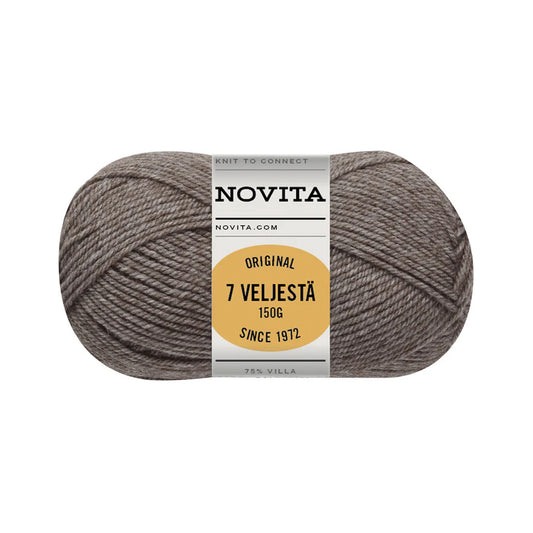こんばんは、細野カレンです。
きょうは、編み物道具のひとつ「輪針」について、少しお話ししてみたいと思います。
輪針は、その名のとおり、両端に針がついたコード状の道具です。
目の数が増えても、重みがコードに分散されるため、手や腕への負担がぐっと軽くなります。
長い作品を編むときも、針先から目が落ちにくく、安心して編み続けられるのが大きな魅力です。
実はアメリカでは、1918年に輪針の原型にあたる特許が出願されていました。
提出したのは一人の女性。
当時の主流だった長い棒針に代わって、毛糸玉と一緒に持ち運びやすく、膝の上で支えられるような道具を考案したのでしょう。
ただ、当時のコードは現在のように柔らかくはなく、しなやかな使い心地になるまでには、時代を経る必要がありました。
日本で輪針が広がったのはもっと後のこと。
昔ながらの平編みや棒針文化が根強く、「輪針で一気に編む」という発想そのものが浸透していなかった時代が長く続きました。
それが少しずつ変わってきたのは、海外のパターンに触れるようになった平成以降。
直線的な往復編みに慣れた感覚が、円を描くように編む技術に出会い、自然と視野を広げていったのかもしれません。
道具が違えば、仕上がりも、編むときの姿勢も、そして時間の流れ方も少し変わってきます。
輪針は、ただの“便利な針”ではなく、「どう編みたいか」という視点そのものに、静かに問いかけてくれるような存在です。
輪針で編む心地よさを知りたい方はこちらをご覧ください。
輪針のコレクションを見る